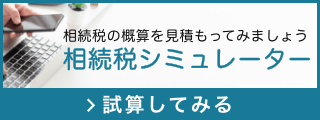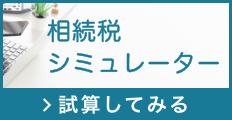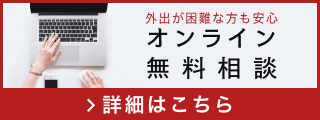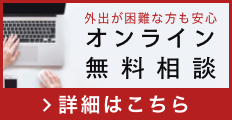2009年の邦画の興行収入が、3年ぶりに前年を上回りました。
立体的に見える3Dとか、ゲームの延長のような速いテンポのバーチャルシーン全盛の外国映画に、食傷気味の方が少なくないということの表れでしょうか。
「劔岳 点の記」(東映)、「HACHI 約束の犬」(松竹)、「火天の城」(東映)、「沈まぬ太陽」(東宝)、「ゼロの焦点」(東宝)など、ヒットの目安である10億円を超す興行収入の作品が相次ぎました。なかでも、山崎豊子さんの同名小説を映画化した「沈まぬ太陽」は、09年最大のヒット作で約30億円を稼ぎ出しました。その効果もあってか、東宝の興行収入は過去2番目の好成績を記録しました(過去最高は2008年で、「崖の上のポニョ」が超大ヒット)。
ちなみに東映の09年最大のヒット作は「劔岳」。黒沢映画の撮影で有名なキャメラマン・木村大作がメガホンをとった2年がかりの大作で、特撮などは一切使用せず、すべて“生身の映像”で迫った作品です。地味なテーマながら、約26億円の興行収入をあげました。
これらの作品に共通しているのは、人間ドラマを落ち着いた映像でしっかりと描いていることです。そして、そんな映画を観ようと映画館に足を運ぶのは50代以上の、いわゆるシニア層の人たちでした。もともと彼らは、若かりし頃、昼食を抜いてでも映画が観たいと夢中になったほどのシネマ世代でもあります。彼らこそが、後でDVDやテレビ放映で観ればいいと思わずに、わざわざ映画館に行ってまで観ようと思える作品を渇望していたにちがいありません。シニア層の映画館離れは、決して映画離れではなく、観たくとも観たい作品がなかっただけといえます。
映画製作・配給各社がシニア層に着目するきっかけとなったのは、2008年に公開され、米アカデミー賞に輝いた「おくりびと」(松竹)でした。この映画のヒットが、眠っていたシニア層の人たちの“シネマごころ”を目覚めさせ、再び映画館へと足を向けさせ、昨年の邦画の健闘と来館者増につながったと言っても過言ではありません。
たしかに興行収入の面から見ると、若者向け人気テレビドラマを映画化した作品が稼ぎ出す額は、シニア向け作品を大きく上回っているのが現実です。ただ一方で、シニア層に比べると、若者のエンターテイメントの中での“映画”の占める割合は高くなく、その分、移り気で興行的な当たり外れも大きいというリスクをはらんでいるのも現実です。
日本全体の年間映画興行収入が2,000億円弱と縮む一方の中、昨年の好調さが、今後の映画市場を占う象徴的な年となり得るのでしょうか? 2010年も、映画好きなシニア層を狙った日本映画の健闘を期待したいものです。