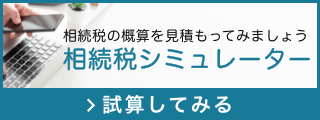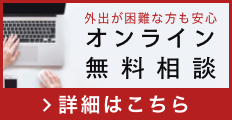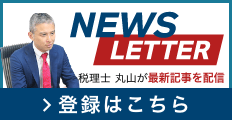[相談]
 当社はこのたび、従業員への福利厚生の一環として社員食堂(当社直営)を設置することになりました。
当社はこのたび、従業員への福利厚生の一環として社員食堂(当社直営)を設置することになりました。
その社員食堂における従業員からの食事代徴収額については、所得税法上の非課税限度額を参考に決定したいと考えています。
そこで、上記の社員食堂において、会社が従業員に食事を(現物で)支給した場合における所得税法上の非課税限度額の判定方法の概要を教えてください。
[回答]
ご相談の社員食堂における食事の支給(現物支給)にかかる経済的利益が所得税法上非課税とされるかどうかについては、①従業員等から食事代として徴収した金額がその食事の材料等に要する直接費の額の50%以上であるかどうか、②その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額から従業員等から食事代として徴収した金額を控除した残額が(税抜で)月額3,500円以下であるかどうか、これらの2つの要件を満たしているかどうかにより行うこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法では、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、原則として、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とすると定められています。
したがって、給与所得の収入金額には、金銭で支給されるものだけでなく、食事の支給などの経済的利益(いわゆる現物給与)も、原則として含まれることになります。
使用者(会社)が役員又は使用人(従業員)に対し支給した食事(残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます)につき、①その役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、一定の方法により評価したその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、②その食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下である場合には、その役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする(=その経済的利益には所得税が課税されない)こととされています。
使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価することとされています。
①使用者が調理して支給する食事
…その食事の材料等に要する直接費(食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用)の額に相当する金額
②使用者が購入して支給する食事
…その食事の購入価額に相当する金額
また、使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が非課税限度額(月額3,500円)以下であるかどうかの判定は、消費税(および地方消費税)の額を除いた金額(=税抜金額)をもって行うこととされています(なお、その税抜金額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てることとされています)。
したがって、今回のご相談の社員食堂における食事の支給(現物支給)にかかる経済的利益が所得税法上非課税とされるかどうかについては、①従業員等から社員食堂での食事代として徴収した金額がその食事の材料等に要する直接費の額の50%以上であるかどうか、②その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額から従業員等から食事代として徴収した金額を控除した残額が(税抜で)月額3,500円以下であるかどうか、これらの2つの要件を満たしているかどうかにより行うこととなります。
[参考]
所法36、所基通36-38、36-38の2、平元直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。